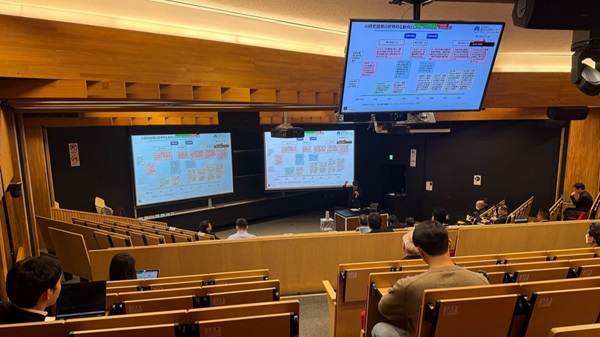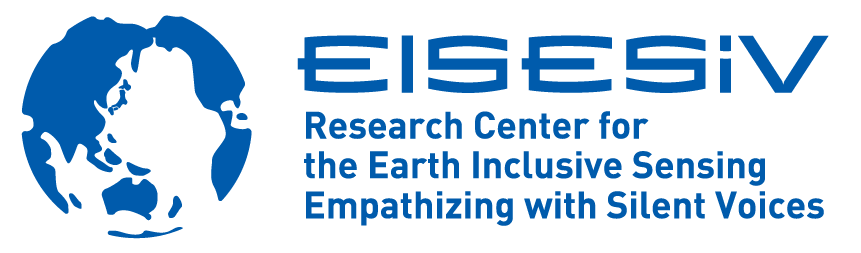

NEWS
EISESiV・iSyMsコンソーシアム合同シンポジウムを11月18日に大岡山キャンパス石川台三島ホールにて開催しました。昨年に引き続き3回目となります。当日は大学や研究機関、企業から会場で30名余り、またZoomによる参加が40数名とたくさんの方が参加していただき厚く御礼申し上げます。今年は東京工業大学と東京医科歯科大学が東京科学大学として統合されたことに伴い、医療系の話題を取り入れ「AIとサイレントボイスが支える私たちのウェルビーイング」をテーマとして講演をおこないました。

まず仁科院長の挨拶に続き、国立がん研究センター研究所 医療AI研究開発分野 分野長の浜本 隆二 先生より「臨床医学へのAI導入:研究立案から薬事承認まで」の題目で基調講演をしていただきました。
講演では現在医療AIが非常な勢いで進展しており、特にシカゴ大学は伝統的に放射線医学が進んでおり、レントゲン、CTやPETといった画像診断分野の研究では中心となっているとのことであった。またAIに対してその可能性への期待とともに危険性も踏まえ人間もしっかり使い方を考えることが必要との持論も言及されておられました。
医療AIと保険制度に関して、米国は格差社会でであり医療AIを導入することにより裕福な患者だけでなく多くの患者に対し医療診断の機会を与える可能性を示唆していることや、日本は皆保険制度が導入されている一方、それをサステナブルなものにするために医療AIをどのように適用すべきか検討がなされていることの説明がなされました。さらに、我が国の医療介護分野におけるAI戦略が紹介され、医療機器、例えばAIを搭載した内視鏡画像診断支援ソフトウエアがこれまで多く薬事承認されていることや、また医療機器の開発にあたり医療デジタルデータを扱う上で個人情報保護法との関係、その開発に対すガイドラインの策定など医療制度や開発研究に関する興味深い内容でした。
次に招待講演として、東京科学大学 工学院 電気電子コース荒井慧悟 准教授より「固体量子センシングによる生体電流イメージングの可能性」のテーマで講演をしていただきました。
新しいバイオセンシングの技術としてダイヤモンドセンサに関する紹介で、NVセンターをもつダイヤモンドはその量子ビットの性質を応用して微小な磁場の測定に応用できること、また磁場以外にも電場、温度、圧力といった計測も常温で可能という特徴をもつことなど説明され、その実用例として細胞及び心臓に対する磁場計測の実験が紹介されました。細胞に関しては生きているバクテイヤの磁力線やイカの電流などを観測したこと、心臓に関しては、ネズミを使ってその心臓を磁場で測定し見える形でセンシングできたことで、今後心臓欠陥の判断として有用な心臓のどの部分に電流が回っているかにより欠陥部位の判断など心磁計への開発につながる手がかりをつかめたとの報告がなされた。


基調講演に続き、EISESiVコンソーシアムのリーダーである東京科学大学 廣井 聡幸 特任教授の司会の下、各コンソシャムのメンバーから次に示す3件の講演がなされました。
・パーキンソン病の治療に向けた運動センシングとリハビリの創出サイクル
東京科学大学 情報理工学院 情報工学系 知能情報コース 三宅 美博 教授
・サイレントボイスを聴くための集積回路技術
東京科学大学 総合研究院 ナノセンシング研究ユニット 教授 伊藤 浩之 教授
・超高感度計測を実現するバイオハイブリッドセンサ
東京大学大学院 情報理工学系研究科 竹内 昌治 教授
東京科学大学の三宅教授から歩行分析と歩行改善の2つのテーマで話されました。
まず歩行改善はこれまでロボットを用いて主に歩行治療を研究してきたが、ロボットによる歩行アシストで歩行能力に改善が見られたが、最近では座ったままでロボットによるリハビリでも改善効果が表れたことが新しい。
歩行分析については計測方法として足首と首筋だけに慣性センサーを付けただけでどこでも測定できるようになったほか、画像を使うことで3次元のセンシングも可能となったとのことである。
会場からの質問で、関節障害治療後のリハビリにおける歩行訓練への応用、さらにシューフィッターにおける歩行観測などビジネスに展開できるのではないかとの意見も出されました。
東京科学大学の伊藤教授からは、アニマルウェルフェアで牛の首に加速度センサーを付け、その測定データをAIで解析して牛の行動を推定する技術を開発していることが紹介されました。また加速度センサーに対する高感度化としてノイズ低減、容量利得の向上といった改善策のほか、データ処理におけるアナログフロントエンド回路の開発などで超低消費電力による高感度センサーで様々な応用が期待されるとのことでした。
東京大学の竹内教授からは、生物と機械の融合といった研究開発が紹介された。例えば犬の嗅覚、細胞の自己増殖や脳とか筋肉におけるエネルギー効率が高いことなどを応用することで機械だけでは実現できないセンサーやロボットを開発しているとのことでした。その実例として、蚊の人の汗に反応する嗅覚受容体を使ったバイオセンサーや、実際に肝臓癌の呼気に反応する蚊の嗅覚受容体を使って癌のマーカーとして利用できる例が紹介されました。



これらの講演の後、EISESiVコンソーシアム・iSyMsコンソーシアムのサブリーダーである東京科学大学 若林 整 教授より各講演の内容を簡潔に整理するとともに、今回のシンポジウムのテーマであるウェルビーイングと非常に密接した話題であったとのまとめがなされました。
最後にiSyMsリーダーである東京科学大学 平本 俊郎 特定教授より、東京科学大学が統合されたことによりAIと医療の融合といった点で有益な講演がなされたことで各講演者に対するお礼とともに今後の更なるご理解・ご協力をお願いして閉会となりました。